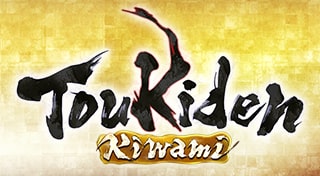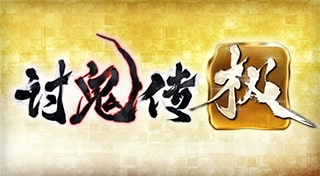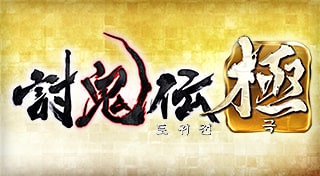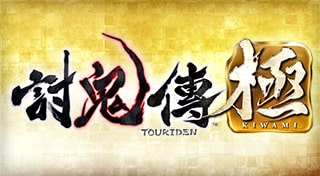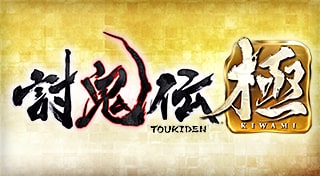转载请在明显位置注明本帖链接
161-180

(だいこくやこうだゆう)大黒屋光太夫
江戸時代後期の船頭。伊勢国出身。江戸に向かう途中嵐に遭い漂流。ロシア人に助けられる。時のロシア女帝・エカチェリーナ2世に謁見、許しを得、10年のロシア生活を経て帰国した。

(らいでんためえもん)雷電爲右エ門
江戸時代中期の力士。大相撲史上最強とされる。信濃国出身。本場所36場所に出場し優勝が28回。その間、黒星は10のみ。勝率は史上1位の9割6分2厘で、さらに9連続優勝の記録を持つ。

(にのみやそんとく)二宮尊徳
江戸時代後期の農政家。薪を背負い本を読む二宮金次郎像こそ少年時の尊徳である。小田原の地主の子に生まれる。水害により田畑が壊滅したのを「報徳思想」に基づき再建。

(くにさだちゅうじ)国定忠治
江戸時代後期の侠客。赤城を中心に上野、信濃にわたる地域を実質支配した。その地域は「盗区」と呼ばれ、忠次を取り締まる側の幕府の役人から治安の良さを絶賛されている。

(じらいや)児雷也
江戸時代後期に刊行された読本の登場人物。初出の表記は自来也。天下征服を狙う妖賊・大蛇丸に父を殺された児雷也は、同じ境遇の少女・綱手と共に、仙素道人に師事。

(ゆいしょうせつ)由井正雪
江戸時代前期の思想家。楠木流軍学者。当時3代将軍・徳川家光までの大名家取りつぶし政策により、牢人が増え社会不安が増大していた。家光の死を機に、蜂起を企んだが密告により露見し、自刃した。

(よしのだゆう)吉野太夫
江戸時代初期の太夫(遊女、芸妓の最高位のこと)。京の花街・六条三筋町「七人衆」の筆頭で、夕霧太夫、高尾太夫とともに寛永三名妓といわれる。和歌、琴、茶道など、様々な芸事を極めた才女。

(けいしょういん)桂昌院
江戸時代初期の女性。5代将軍・徳川綱吉の母。名は玉。江戸幕府3代将軍・徳川家光の側室のお万の方に仕えていたが、家光に見初められ側室となる。綱吉を生んで大奥の実権を握るに至った。

(さかもとりょうま)坂本龍馬
江戸時代末期の武士。土佐藩の郷士出身。商社・亀山社中(のちの海援隊)を組織した。明治維新の大方針となる「船中八策」を発案、大政奉還を成し遂げたが、維新前年、京・近江屋で暗殺された。

おりょう
江戸時代末期から明治時代の女性。坂本龍馬の妻。名前に龍の字が入っているのが出会いのきっかけだったという。寺田屋事件では入浴中に囲まれているのに気づき、裸で龍馬を逃がして命を救った。

(さかもとおとめ)坂本乙女
幕末から明治時代の女性。土佐藩郷士の娘で坂本龍馬の姉。剣術・馬術、琴・三味線など文武両道に秀でていた。大柄な女性で「お仁王様」と呼ばれていた。母没後、龍馬の母代わりを務めた。

(なかおかしんたろう)中岡慎太郎
江戸時代末期の武士。幕末の志士。陸援隊隊長。土佐で郷士身分の大庄屋に生まれる。学問と剣術を修めたのち政治活動を開始。薩長同盟を結実させ、また薩土倒幕の密約を成立させた。

(かつかいしゅう)勝海舟
江戸時代末期から明治時代初期の政治家。幕臣。戊辰戦争時、新政府軍が江戸に迫ると、内乱の長期化と国家分裂を危ぶみ、早期停戦と江戸城の無血開城を主張。江戸城の無血開城を成し遂げた。

(たかすぎしんさく)高杉晋作
江戸時代末期の武士。長州藩士。吉田松陰の松下村塾に学んだ幕末の志士。下関戦争の後、奇兵隊を創設。藩政を握り幕府の長州征伐軍を撃退。倒幕の気運を高めた。

(いわさきやたろう)岩崎弥太郎
明治時代初期の実業家。三菱財閥の創始者にして初代総帥。土佐藩出身。明治維新後は政商として暗躍。台湾出兵、西南戦争などの軍事輸送を引き受けて利益を上げ、明治政府の発展にも大きく寄与した。

(ちばさなこ)千葉さな子
幕末から明治時代にかけての女性。北辰一刀流創始者・千葉周作の姪。江戸に剣術修行に来ていた坂本龍馬と知り合って恋仲となり婚約。やがて龍馬とは疎遠になるが、龍馬が暗殺されたあとも慕い続けていたという。

(こんどういさみ)近藤勇
江戸時代末期の武士。新撰組局長。京の尊皇攘夷志士を取り締まった。新政府軍が江戸に迫ると、迎撃に向かうが、これは近藤ら抗戦派を排除したい勝海舟ら和平派の罠で、衆寡敵せず敗退。

(ひじかたとしぞう)土方歳三
江戸時代末期の武士。新撰組副長。冷静な判断力で実質的に新撰組を指揮していた。厳格な局中法度で隊士を律し、背く者には切腹、斬刑で臨んだ。戊辰戦争では幕府軍の指揮官として活躍。

(おきたそうじ)沖田総司
江戸時代末期の剣術家。新撰組一番隊組長。剣の名手で、天然理心流を使い、撃剣師範を務める。剣術道場・試衛館に入門し、近藤勇や土方歳三と知り合い、彼らの新撰組結成に従う。

(さいとうはじめ)斎藤一
江戸時代末期の武士。新撰組三番隊組長。剣の名手で、「沖田は猛者の剣、斎藤は無敵の剣」と評された。新撰組内部の粛清や伊東甲子太郎の御陵衛士潜入に活躍。